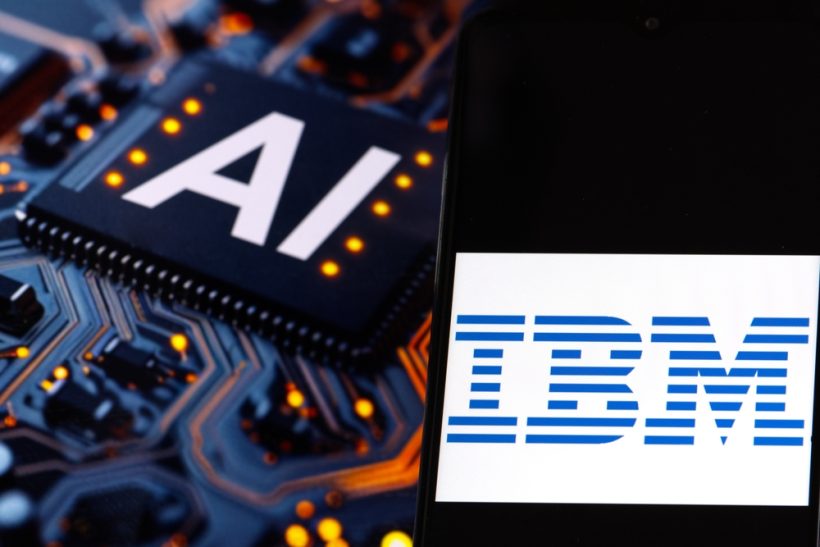
IT世界大手米IBMと国連開発計画(UNDP)は9月17日、電力アクセス予測AIモデルを開発したと発表した。UNDPが提供しているオープンデータベース「GeoHub」上で、データを公表していく。
今回開発したAIモデル「電力アクセス予測」は、IBMの環境インテリジェンスが提供する土地利用データに加え、人口、インフラ、都市化、標高、衛星データも活用。アフリカ、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東を含む「南半球」の102カ国に関し、2030年までの電力アクセスの予測できる。すでに入手可能な電力アクセスに関する現行の推計モデルよりも、精度が高いという。
さらに、IBMとUNDPが、ストーニー・ブルック大学とともに開発した「クリーンエネルギー公平性指数」も表示。同指数は、アフリカ53カ国を対象に、教育、温室効果ガス排出量、相対的豊かさ等の環境、経済、社会的要因と、地理空間分析を組み合わせた世界初の統計地理空間モデルで、クリーン・エネルギー公平性スコアを0から1の範囲で算出する。また、GeoHubのユーザーは、モデルで分析された環境、経済、社会の各要因を個別に表示、カスタマイズすることもでき、どの要因がクリーンエネルギーへの公平なアクセスに最も大きな影響を与えるかを知ることもできる。
IBMは、IBMが2022年に開始した社会的インパクト・プログラム「サステナビリティ・アクセラレーター・プログラム」を通じ、UNDPと2年間協働。AIモデル「電力アクセス予測」と統計地理空間モデル「クリーンエネルギー公平性指数」の開発につながった。
またIBMと米航空宇宙局(NASA)は9月23日、オークリッジ国立研究所の協力を得、気象・気候の様々な事象に対応する新たなAI基盤モデル開発したことも発表した。短期的な気象や長期的な気候予測までを扱うことができ、局所的な観測に基づく的を絞った予報、悪天候パターンの検出と予測、地球規模の気候シミュレーションの空間解像度の向上、数値気象・気候モデルにおける物理プロセスの表現方法の改善等が可能となる。
同AIモデルは、NASAが過去40年間蓄積してきたデータベース「Modern-Era Retrospective analysis for Research and Applications, Version 2(MERRA-2)」を訓練データとして活用。地球規模、地域規模、ローカル規模に調整できる独自のアーキテクチャを備えた基礎モデル「Hugging Face」と、応用アプリケーションモデルとして「気候・気象データのダウンスケーリング」「重力波パラメタリゼーション」の2つが用意されている。3つ全て公表されている。
IBMは別途、カナダ環境気候変動庁(ECCC)とも協働しており、降水ナウキャスティングと呼ばれる手法を用いて、リアルタイムのレーダーデータを入力することで超短期降水予測が可能となるモデルを模索している。15kmからkmスケールの解像度で全球モデル予測からのダウンスケーリング手法もテストしている。
【参照ページ】UNDP and IBM Launch New Tools to Forecast Energy Access and Model Energy Equity
【参照ページ】IBM and NASA Release Open-Source AI Model on Hugging Face for Weather and Climate Applications
今なら無料会員にご登録いただくだけで、
有料記事の「閲覧チケット」を毎月1枚プレゼント。
登録後、すぐにご希望の有料記事の閲覧が可能です。
または
有料会員プランで
企業内の情報収集を効率化
- ✔ 2000本近い最新有料記事が読み放題
- ✔ 有料会員継続率98%の高い満足度
- ✔ 有料会員の役職者比率46%
有料会員プランに登録する
Sustainable Japanの特長
Sustainable Japanは、サステナビリティ・ESGに関する
様々な情報収集を効率化できる専門メディアです。
- 時価総額上位100社の96%が登録済
- 業界第一人者が編集長
- 7記事/日程度追加、合計11,000以上の記事を読める
- 重要ニュースをウェビナーで分かりやすく解説※1
さらに詳しく
ログインする
※1:重要ニュース解説ウェビナー「SJダイジェスト」。詳細はこちら
 Skip navigation
Skip navigation
 Skip navigation
Skip navigation